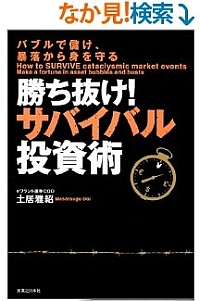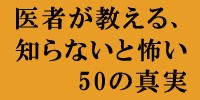リオデジャネイロでオリンピックが閉幕した。連日のメダルラッシュに日本中が沸いたが、そんなイベントに水を差す事件があったことを覚えている人も多いだろう。ロシアが国家主導でドーピング隠しをしていたことが発覚し、一部のロシアの選手がオリンピックに出場できなくなった事件だ。
「金メダルが取れるならドーピングで死んでもよい」が過半数
「五輪で金メダルを取れるならば、5年後に死ぬとわかっていてもドーピングするか?」の質問に過半数が「イエス」と答えた。
そんな衝撃的な調査結果がアメリカででた。
調査を行ったのは米スポーツ医学協会(NASM)の創設者でもあるボブ・ゴールドマン氏。1980年代に世界レベルのスポーツ選手198人を対象に質問したところ、過半数が「イエス」と答えた。その後10年にわたり、2年ごとに同じ調査が行われたが、約半数が「イエス」と答える結果に変わりはなかった。

一般人なら健康のためのスポーツも、トップアスリートにとってはまるで意味が違う。スポーツとは、ある者には名誉のために、ある者には大金のために全てをかけるものなのだ。オリンピックの大舞台ともなると、そこに国家の思惑と名誉まで加わるから、ドーピングの闇は深く進化は凄まじい。この問題の根底には、イタチごっこになっている禁止薬物リストの問題がある。例えば、テニスのマリア・シャラポアのドーピングで話題になったメドニウムも、シャラポアのドーピングが発覚する今年の1月まで禁止薬物リストに入っていなかった。禁止薬物リストに入った時点でシャラポアはドーピングとなったが、それまで10年にわたりメドニウムを摂取していたと言われている。
禁止薬物リストにない新しい化学物質なら、ドーピングとならない。だから、新規化合物や既存の化合物の構造を少し変えた化合物が次々に登場することになってしまう。まさに、脱法ドラッグと同じことがドーピングでも起こっているわけ。五輪が世界の注目を浴びる限り、今後もこういう流れはなくならないだろう。
遺伝子改良アスリートがメダルを独占する未来
さらに、近年の医療・化学の進歩がドーピング規制をより難しくしている。
化学物質を使ったドーピングのほかに、最近では遺伝子ドーピングなんて言う技術も確立されてきている。これは競技能力を高めると予想される遺伝子を選手に組み込み、遺伝子を操作するドーピングだ。例えば、2004年に発見された技術が有名だ。これはPPARデルタという脂肪を燃焼させるタンパク質が多くなるように改良した遺伝子をマウスに組み込む技術だ。その結果、マウスが通常のマウスの2倍の距離を走ることが発見された。このマウスは「マラソンマウス」と言われて、当時のメディアを賑わせた。ほかにも一昨年のノーベル賞で話題になったiPS細胞も筋肉細胞を増やしたりできるわけで、当然ドーピングへの悪用が懸念されている。これらの技術は本来、筋力が衰えた病人や高齢者のために応用されるべきものだが、理論的にはドーピングにも応用可能で確実に効果的だ。だって、体そのものを改良してしまうのだから。効果的に使いこなせれば、天然由来のアスリートでは太刀打ちできないだろう。

化学物質を使ったドーピングは検査で禁止物質が特定できればドーピングと分かるが、遺伝子そのものを改良するドーピングは見つけるのが困難だ。例えば、ある選手から筋力を増強するタンパク質が多く見つかったとしても、選手が元から持っている遺伝子由来のものなのか遺伝子ドーピングで持ったものなのか判断することは非常に難しい。
マラソンマウスの技術はヒトへの応用はできていないようだが(サルを使った実験では副作用が出すぎて、最終的には安楽死させるしかなかったようだ)、この分野の進歩は著しい。東京五輪くらいにはとても巧妙で検出不可能なドーピングが出てきても不思議ではない。今回の五輪で遺伝子改良アスリートが参加しているかどうかは僕にはわからない。しかし、一つだけ言えるのは、アスリートにとって遺伝子操作は魅力的な技術であるということだろう。今日もリオで偉大な記録を残したアスリートが生まれている。その記録が生化学の粋を極めた「遺伝子改良アスリート」によるものでないことを祈るばかりだ。
某大手食品メーカー研究室に勤務。
学生時代、実験でスペルミジンの合成に成功するも、衣服に付いたその臭いで変態呼ばわりされた苦い過去を持つ。
学生時代に得た「化学のすすめ」を合い言葉に、日常生活における化学を一般の人にわかりやすく伝えたいと日々尽力する化学オタク
- |HOME|

![code-G[コードG]](/files/images/common/logo.jpg)