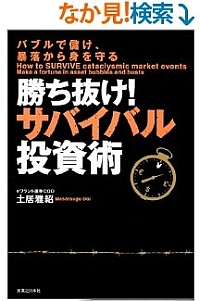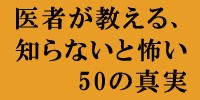「スクール・オブ・ロック」
北朝鮮への渡航歴が20回を越える荒巻は、あの国の映像をのべ1000時間以上撮り溜めていて、「この国は大きく変わる」と肌で感じていた。その「時代の変化」を映像で伝える人間はどうしても日本人でなくてはならず、しかもいきなり日本などから連れて来られて「街に拒絶」されてしまうようでは使い物にならない、だから共産圏で暮らしている日本人でなけらばいけないのだと言う。
「映像を撮り溜めている」と聞くと隠し撮り映像をテレビとかに売りつけている輩を想像してしまうが、荒巻は自分は中国の大学に籍を置く「研究者」であると言う。専門は東アジア学、中でも北朝鮮とチベットが専門であると言う。

「日本に本当の意味の北朝鮮の社会学専門家というのはいないんです。あえて言うと実際にフィールドワークを展開しているのは世界中で僕しかいません。僕はこの経験から導き出す自分の理論を学会に発表して、今あるステレオタイプ化した北朝鮮の概念を覆すために、10年以上あの国に行き続けているんです」
難しいアジアと北朝鮮論をひとしきり喋った後に
「とりあえずこれ見といて下さい」
荒巻からぽんと渡されたのは1枚のDVD。
「スクール・オブ・ロック」
ハリウッドの映画で、食えないロックミュージシャンが間違いで優等生の高校教師になってしまい、結局はその高校をロックに染めてしまうという映画である。
私は「ロック」という言葉に弱い。すぐに心動かされる。「ロック」とつけば何でも正しいと感じるぐらいそれは偏執的だった。
私が生まれたのは1959年なので、いわゆるウッドストックやヒッピー文化よりは少し後である。また生まれ育ったのが四国は香川県の片田舎だったので、学生運動やそういう情報もあまり入って来ず、レコード店にも「ロック」や「ジャズ」というジャンル分けもない時代だったので、正直言って何が「ロック」なのか「ジャズ」なのかよくわかっていない。初恋の人に振られたことにより大学を中退して、「東京に行ってロックをやる」か「ニューヨーク行ってジャズをやる」か、その程度の漠然とした感覚でしかなかった。
しかし結局は黒人音楽に傾倒し、「俺は黒人になる!!」と豪語しながら髪型をアフロヘアーにして「ファンキー末吉」と名乗ってたんだから、何を持って「ロック」なんだという話である。

最初に中国に来た時は「ロックはないか?」と毎日探し歩いた。会う人会う人に拙い英語で聞いたが、答えは「没有(メイヨウ)」だった。
最終日に諦めて、仲良くなったホテルのボーイに
「お前達若者がいつも遊んでいるところに連れて行ってくれ」
と頼んだ。
ボーイは周りを気にしながら、
「じゃあ、仕事終わったらホテルの裏口で会いましょう」
と小声で言った。天安門事件の次の年、1990年当時の中国では、まだ人民が外国人と、ましてやボーイと客が親しくすることはあまり歓迎されることではなかったのである。
連れて行かれたのは「音楽茶座」。何てことない、カラオケが置いてあるパブのようなところであった。毎日「ロックはどこにある?」と聞いて来た音楽好きであろう外国人を連れて来るには、ボーイはここが最適だと思ったのだろう。
私はもうロックを探すのは諦めて、そこに腰を据えて飲み始めた。カラオケは中国の曲だけでなく欧米の曲もかかっていたが、当時流行っていたマドンナのカラオケ映像には、ちょっとセクシーなシーンにもすべてモザイクがかかっていた。そんな「時代」だった……。

ホームページ:Funky末吉HomePage!!
本:平壌6月9日高等中学校・軽音楽部 北朝鮮ロック・プロジェクト
プロローグ 北朝鮮?いいですよ、行きましょ!!
第一章 平壌をロックに染めてやる!
第二章 北朝鮮初のオリジナル・ロック曲
第三章 チベットで発見した「ロックとは何か」
第四章 次世代の部員との本気のセッション
第五章 新人類たちとのロック
第六章 はるかなる北朝鮮-さようなら愛弟子たち
プロローグをスマホで
iPhone・androidの方はこちら
※iPhoneはiOS6とiBooks、androidはReaderアプリが必要です
iPadの方はこちら
※iOS6とiBooksが必要です
- |HOME|

![code-G[コードG]](/files/images/common/logo.jpg)